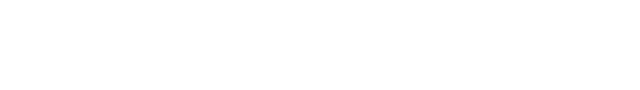その「のどのつかえ感」、もしかしたら食道のアレルギーかもしれません/内視鏡専門医が解説
ハイサイ!安謝ファミリークリニック院長の高良です。
「食べ物が飲み込みにくい」「のどに何かがつまっている感じがする」
このような症状で医療機関を受診すると、多くの場合、耳鼻科でのどの感染症や、消化器内科で逆流性食道炎と診断されます。また、特に異常が見つからず「ストレスですね」と言われることも少なくありません。
しかし、これらの症状の裏には、まだあまり知られていない「好酸球性食道炎(こうさんきゅうせい しょくどうえん)」という病気が隠れている可能性があります。これは、食物などが原因で起こる、食道の慢性的なアレルギー性炎症です。
この記事では、近年診断されることが増えてきた「好酸球性食道炎」について、その原因から最新の治療法まで、詳しく、そしてわかりやすく解説します。
1. 好酸球性食道炎って、どんな病気?
一言でいうと「食道のアレルギー」
私たちの血液中には、細菌やウイルスと戦う「白血球」という免疫細胞がいます。その一種に「好酸球」という細胞があります。
-
好酸球の本来の役割: 主に寄生虫を攻撃したり、アレルギー反応に関わったりする兵隊のような細胞です。
-
好酸球性食道炎で起こっていること: 本来は無害なはずの食べ物や、花粉・ハウスダストなどに対して、この好酸球が過剰に反応。大挙して食道の粘膜に集結し、そこでアレルギー性の炎症を起こしてしまいます。
この慢性的な炎症によって食道の壁が硬くなったり、正常な蠕動(ぜんどう)運動(食べ物を胃に送る動き)が妨げられたりすることで、食べ物のつかえ感などの症状が現れるのです。
(右から好中球、好酸球、好塩基球、リンパ球、単球です。)
日本ではどのくらいの人がいるの?
好酸球性食道炎は、かつて日本では非常にまれな病気と考えられていました。しかし、内視鏡(胃カメラ)の性能向上や医師の認知度向上により、近年報告数が急増しています。
本邦検診施設からの最近の報告では有意な自覚症状がない検診上部内視鏡受診者約5,000例のうち0.4%(400人/10万人)に食道好酸球浸潤が発見されています。これは250人に1人程度の割合であり、決して無視できない数字です。症状のある方ではさらに有病率が増えることが予想されます。おそらく、これまで「原因不明のつかえ感」とされていた方の中に、多くの患者さんがいたと推測されます。(有症状者の有病率は報告によりばらつきが大きいです。)
2. どんな人がなりやすいの?(特徴とリスク因子)
好酸球性食道炎には、いくつかの特徴的な傾向があります。
-
好発年齢・性別: 30代後半から40代の男性に最も多く見られます。
-
アレルギー体質: 患者さんの多くが、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎(花粉症など)といった他のアレルギー疾患を合併しています。ある報告では、患者の7割以上が何らかのアレルギー疾患を持っていたとされています。
-
ピロリ菌との不思議な関係: 胃がんの原因となるヘリコバクター・ピロリ菌ですが、不思議なことに好酸球性食道炎の患者さんは、ピロリ菌に感染していない(未感染)場合がほとんどです。これは、ピロリ菌がいない衛生的な胃の環境が、逆にアレルギー反応を起こしやすくしているのではないか、という説(衛生仮説)もあります。
3. どうやって診断するの?(検査と診断の流れ)
診断は、「①特徴的な症状」「②内視鏡検査での所見」「③生検による確定診断」という3つのステップで進められます。
ステップ1:症状の確認
まず、以下のような症状がないかを確認します。
-
食べ物のつかえ感、飲み込みにくさ(嚥下困難) ← 最も代表的な症状
-
胸のあたりで食べ物が止まる感じ
-
胸やけや、胸の痛み
-
(まれに)食べ物が完全につまってしまう「食物嵌頓(しょくもつかんとん)」
症状の強さには個人差があり、「水分も通りにくい」と強く訴える方もいれば、「言われてみれば、つかえることがあるかも」という程度の方もいます。
ステップ2:内視鏡検査(胃カメラ)
食道の中を直接カメラで観察し、特徴的な見た目のサインを探します。同時に、食道がんや重度の逆流性食道炎など、他の病気ではないことを確認する上でも極めて重要です。
【好酸球性食道炎に特徴的な内視鏡所見】
-
縦走溝(じゅうそうこう): 食道に縦方向のシワや溝ができる。
-
輪状溝(りんじょうこう): 木の年輪や蛇腹のように、横方向の溝がいくつも見える。
-
白色滲出物(はくしょくしんしゅつぶつ): 好酸球が集合してできた、白いブツブツとした斑点が粘膜に付着している。
-
粘膜浮腫(ねんまくふしゅ): 粘膜がむくんで腫れぼったくなり、本来見えるはずの血管が透けて見えなくなる。
-
狭窄(きょうさく): 炎症が長く続くことで食道が硬くなり、内腔が狭くなる。
ステップ3:生検(組織検査)による確定診断
内視鏡で疑わしい所見が見つかった場合、その部分の組織を米粒の半分ほどの大きさで数カ所つまみ取ります。これを「生検(せいけん)」または「バイオプシー」と呼びます。
採取した組織を顕微鏡で詳しく調べ、食道粘膜に多数の好酸球(1視野あたり15個以上が基準 ※この場合の視野はHPFのことです。HPF: 顕微鏡の400倍、1視野)がいることを確認できれば、「好酸球性食道炎」という診断が確定します。
4. どんな治療法があるの?
治療の目的は、食道の炎症を抑え、つかえ感などの症状をなくし、快適な食生活を取り戻すことです。
第一選択:プロトンポンプ阻害薬(PPI)
最初に試されるのは、逆流性食道炎の治療にも使われる胃酸を抑える薬(PPI)です。意外に思われるかもしれませんが、この薬は胃酸を抑えるだけでなく、食道の炎症を直接抑える効果もあると考えられており、患者さんの半数~7割で症状が劇的に改善します。
第二選択以降の薬物療法
PPIで効果が不十分な場合は、次のステップに進みます。
-
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー(PCAB): PPIよりも強力に胃酸を抑える薬です。
-
ステロイド嚥下療法: 気管支喘息用の吸入ステロイド薬を、吸い込まずに口の中に噴霧し、唾液と一緒にゆっくりと飲み込みます。これにより、ステロイドが食道の粘膜に直接作用して強力に炎症を抑えます。飲み薬と違って全身への副作用が少ない、優れた治療法です。
食事療法
欧米では、アレルギーの原因となりやすい食品(6大アレルゲン:牛乳、小麦、卵、大豆、ナッツ、魚介類)を除去する食事療法が積極的に行われています。しかし、原因食物の特定が難しいことや、日本では薬物療法で良好にコントロールできる患者さんが多いため、食事療法は一般的ではありません。
指定難病について
この病気は「好酸球性消化管疾患」として国の指定難病になっていますが、対象となるのは治療が難しく、日常生活への支障が大きい中等症~重症例です。ほとんどの患者さんは薬で症状をコントロールできるため、過度に心配する必要はありません。
まとめ:長引く「のどの違和感」、一度は内視鏡検査を
もしあなたが、
-
長引く「食物のつかえ感」や「のどのつまり感」に悩んでいる
-
特に、喘息や花粉症などのアレルギー体質である
-
逆流性食道炎の薬を飲んでも症状がすっきりしない
という場合は、好酸球性食道炎の可能性も考えられます。
放置すると、食道がさらに硬く狭くなり、食べ物が完全につまってしまう「食物嵌頓」という救急事態を引き起こすリスクもゼロではありません。
最新の内視鏡技術によって、この病気は以前よりもずっと見つけやすくなっています。自己判断で様子を見たり、ストレスのせいだと諦めたりせず、ぜひ一度、内視鏡検査(胃カメラ)が可能な消化器内科を受診して専門医に相談してみてください。