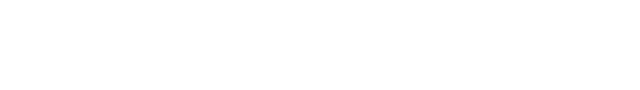大腸憩室炎の症状・治療・予防法|専門医がわかりやすく解説
ハイサイ! 院長の高良です。
大腸憩室炎は、大腸の壁にできた「憩室」が炎症を起こす病気です。
近年、食生活の欧米化や高齢化に伴い、日本でも患者数が増加しています。
今回は、症状や治療法、予防策まで詳しく解説します。
1. 大腸憩室炎とは?
大腸憩室は、腸の壁が外側に袋状に飛び出した状態で、加齢や便秘による腸内圧の上昇が原因で形成されます。
憩室自体は無症状ですが、細菌感染により炎症を起こすと「憩室炎」となり、以下の症状が現れます:
- 腹痛:炎症部位に応じた痛み(右下腹部痛は虫垂炎との鑑別が必要)
- 発熱
- 腹部膨満感
危険因子
- 高齢(60歳以上でリスク上昇)
- 食物繊維不足・赤身肉の過剰摂取
- 喫煙・肥満
2. 診断方法
症状だけでは確定診断できません。以下の検査が行われます:
1. 血液検査:白血球数やCRPの上昇を確認
2. 腹部CT検査・腹部エコー:炎症部位や合併症(膿瘍・穿孔)の有無を評価
3. 大腸内視鏡検査:炎症が落ち着いた後、大腸がんとの鑑別のために実施
※注意点:急性期の内視鏡検査は腸穿孔のリスクがあるため、通常は症状改善後6〜8週間経過してから行います。
3. 治療法:軽症から重症まで
治療方針は炎症の重症度と合併症の有無で決定されます。
軽症(外来治療)
- 絶食または低残渣食:腸管安静を保つ
- 抗菌薬の内服:セフェム系やニューキノロン系が使用される(ただし、軽症では抗菌薬不要の可能性も)
- 経過観察:3日後に症状改善を確認
重症(入院治療が必要な場合)
- 抗菌薬の点滴:主にセフェム系が使用されます。
- 絶食と点滴栄養
- 合併症への対応:
- 膿瘍:経皮的ドレナージで排膿
- 穿孔・瘻孔:緊急手術が必要
※手術適応:再発を繰り返す場合や、腸閉塞・腹膜炎を合併した場合。
4. 再発予防と生活習慣の改善
憩室炎の再発率は約13〜47%と高く、予防が重要です。
予防策
1. 食物繊維を積極的に摂取:1日20〜30gを目標(玄米・野菜・豆類)
2. 水分補給:便秘予防で腸内圧を低下
3. 適度な運動:週3回以上の有酸素運動
4. 赤身肉・加工肉の制限
5. 禁煙・節酒:喫煙は合併症リスクを2.7倍に上昇
避けるべき習慣
- 香辛料やカフェインの過剰摂取
- 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の長期使用
5. よくある質問
Q. 憩室炎は自然治癒しますか?
軽症例では抗菌薬なしでも改善する可能性がありますが、自己判断は危険です。必ず医療機関を受診してください。
Q. 再発を防ぐ薬はありますか?
現時点で確立された薬物療法はありません。生活習慣の改善が最善策です。
Q. 大腸がんとの関係は?
憩室炎自体はがん化しませんが、複雑性憩室炎では大腸がんの合併率が3〜8%と報告されています。内視鏡検査で鑑別が必要です。
まとめ
大腸憩室炎は、適切な治療で多くの場合改善しますが、再発や合併症のリスクを減らすためには**日頃の生活習慣が鍵です。
当院では、内視鏡検査を通じて憩室の状態を詳細に評価し、患者さん一人ひとりに合ったアドバイスを行っています。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。